更新日:2025.08.18
統合失調症で障害年金はもらえないと諦める前に|知っておきたい申請の3つのポイントを解説
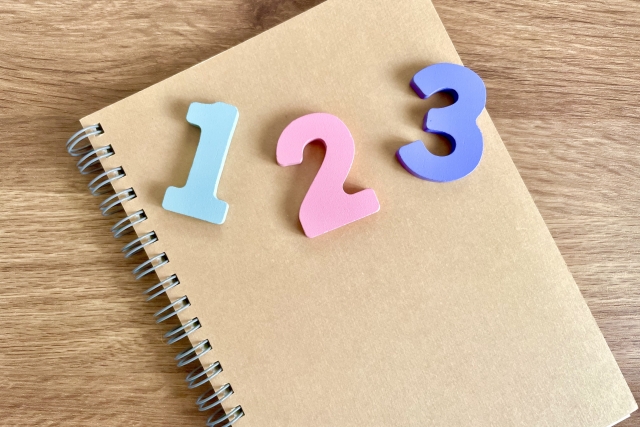
「統合失調症だから障害年金はもらえないかも…」
そんな不安を抱えていませんか?
統合失調症は、考えや気持ちがまとまらなくなる精神疾患で、幻覚や幻聴、意欲の低下などの症状が見られます。
症状が重くなると、日常生活に大きな支障が出たり、働くことが難しくなったりと、経済的な困窮に直面することも少なくありません。
「統合失調症では障害年金を受給できない」と誤解されている人もいらっしゃいますが、結論からお伝えすると、統合失調症は障害年金の支給対象であり、条件を満たせば受給できる可能性は十分にあります。
この記事では、統合失調症の障害年金申請を検討されている人やそのご家族に向けて、「なぜもらえないと誤解されやすいのか」という疑問の解消から申請のポイントを、社労士がわかりやすく解説します。
最後まで読んで、障害年金の知識を深め、あなたの統合失調症での障害年金申請にぜひお役立てください。
目次
統合失調症は障害年金の支給対象
統合失調症は、生活や仕事に大きな影響が出ている場合、障害年金の対象となります。
統合失調症と診断された人が「障害年金はもらえない」と誤解しているケースが見られますが、実際は多くの人が障害年金を受給しています。
統合失調症によって日常生活や仕事が困難になっているのであれば、障害年金を受け取れる可能性は十分にあるのです。
ただし、診断されたら誰でももらえるというわけではなく、障害年金を受け取るためには3つの条件を満たす必要があります。
なぜ統合失調症で障害年金はもらえないと誤解されるの?
「統合失調症だと障害年金はもらえない」という誤解は、主に申請が難しいケースが多いことに起因します。
そのため、あたかも統合失調症では障害年金が「もらえない」かのような話が出回ってしまうのです。
また、「障害者手帳がないと申請できない」「家族の扶養に入っているとダメ」「入院していないともらえない」といった、障害年金制度に関する誤解も根強く存在します。
障害年金は、3つの受給要件をすべて満たせば、障害者手帳の有無や扶養状況に関わらず申請できます。
決して「統合失調症だからもらえない」と諦める必要はありません。
障害年金の3つの受給条件は、のちほど詳しく解説します。
統合失調症で働いていたら障害年金はもらえないの?
結論から言うと、働いていたとしても、障害年金の3つの受給要件をすべて満たせば申請できます。
ただし、働いていると症状が軽いと審査官に判断されがちな傾向はあります。
そのため、診断書や病歴・就労状況等申立書で、以下の点を具体的に、かつ正確に伝える努力が必要です。
- 統合失調症の症状が仕事にどのように影響しているか
- 仕事をする上でどのような困難があるか
- 会社からどのような配慮を受けているか(勤務時間の短縮、業務内容の変更など)
- 周囲のサポートがどれだけ必要か など
「働いているから統合失調症で障害年金はもらえない」と諦めず、障害年金を正しく知り、申請準備を進めましょう。
なお、障害年金を詳しく知りたい人は、障害年金とは?何歳から請求できる?社労士がわかりやすく解説をご覧ください。
統合失調症で障害年金を受給できる3つの条件とは?
統合失調症で障害年金を受給できる3つの条件を表にまとめると以下のようになります。
【障害年金を受給できる3つの条件】
| 初診日要件 | 統合失調症で初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること |
| 保険料納付要件 | 初診日の前日において、一定期間の年金保険料を納付していること |
| 障害状態要件 | 初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)において、国が定める障害等級に該当すること |
これらの3つの要件を正しく理解し、準備を進めることで統合失調症での障害年金受給への道が開けます。
次章でそれぞれ見ていきましょう。
なお、障害年金の3つの受給条件については、障害年金の3つの受給条件とは?年齢は関係ある?わかりやすく解説!でさらに詳しくご説明しているので、ぜひご一読ください。
障害年金の初診日とは?
障害年金における「初診日」とは、障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日のことです。
「統合失調症だから精神科や心療内科が初診日」と考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。
障害の原因となった症状で初めて医療機関にかかった日が初診日となるため、診断名がつく前の受診も含まれるのです。
また「初診日」は、あなたがどの種類の年金を申請できるかを決定する重要な要素となります。
初診日に加入していた年金制度別に申請できる障害年金を下表にまとめました。
| 初診日に加入していた年金 | 申請できる年金 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 国民年金 | 障害基礎年金 | ・自営業 ・専業主婦 ・20歳前に傷病を負った人など |
| 厚生年金 | 障害厚生年金 | ・会社員 ・公務員 |
初診日が特定できない場合、統合失調症で困っていても障害年金が申請できません。
過去の受診履歴をしっかり確認し、正確な初診日を特定することが、障害年金申請の第一歩です。
障害年金の初診日については、障害年金の初診日とは?カルテがないときの対処法もご紹介!で詳細をご説明していますので、ぜひご覧ください。
保険料納付要件とは?
障害年金を受給するためには、初診日の前日までに、一定期間きちんと年金保険料を納めていることが求められます。これが「保険料納付要件」です。
具体的には、以下の2つの条件のうち、どちらか一つを満たしていれば保険料納付要件をクリアできます。
| 3分の2要件(原則) | 初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、3分の2以上の期間について、保険料を納付または免除されていること |
| 直近1年要件(特例) | 初診日に65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと |
ここで重要なのは、初診日以降に慌てて保険料を納めても、それは納付要件の対象とはならない点です。
もし経済的な理由で保険料の支払いが難しい場合は、「未納」にするのではなく、必ず「免除」の手続きをしましょう。
保険料の免除については日本年金機構の公式サイト「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」でご確認ください。
障害状態要件とは?
障害状態要件では、あなたの統合失調症の症状が、国の定める基準に照らして、日常生活や仕事にどの程度の支障をきたしているかを見ています。
審査の際には、診断書や病歴・就労状況等申立書などをもとに、あなたが統合失調症の症状でふだんの生活や仕事においてどのような困難を抱え、どれくらいのサポートが必要とされているのかを評価されます。
単に診断名があるだけでなく、「どれくらい困っているか」を正確に伝えることが不可欠です。
主治医が作成する診断書や、ご自身で記入する病歴・就労状況等申立書といった提出書類がとても重要な役割を担うことがわかるでしょう。
日本年金機構が公開している障害認定基準には、傷病ごとの詳細な基準が示されていますので、より詳しく知りたい人は確認してください。
病歴・就労状況等申立書が自分で書けないときは、社労士がお力添えできます。お気軽にご相談ください。
参考:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
参考:障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
統合失調症の障害認定基準とは?
統合失調症の障害認定基準は、「精神の障害に係る等級判定基準」で定められており、その内容を簡単にまとめると以下のようになります。
※一部を抜粋し、分かりやすく編集しています。原文は日本年金機構が公開している障害認定基準(39ページ)をご覧ください。
| 障害の程度 | 障害の状態(一部抜粋・編集) |
|---|---|
| 1級 | 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |
| 2級 | 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
| 3級 | 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの |
わかりやすく言えば、常に誰かの助けが必要なら1級、日常生活を送るのにかなり苦労するなら2級、仕事に大きな支障があるなら3級、というイメージです。
統合失調症の障害年金審査では、特に「残遺状態」の程度が重視されます。
なお、これらの基準に加えて、個々の状況をより細かく評価するために「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」という別の指針も用いられます。
次章では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」についてご説明します。
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」とは?
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン(以下、ガイドラインと表記)」は、統合失調症などの精神疾患における障害年金の等級を、より詳細かつ公平に判定するための重要な指針です。
このガイドラインは、画一的な基準だけでは測れない個々の状態を評価するために導入されました。
このガイドラインでは、単に病名や症状の有無だけでなく、「日常生活能力の程度」や「就労状況」「治療の状況」など、総合的に評価する際に考慮すべき様々な要素が示されています。
ガイドラインの詳細や障害等級判定の流れは、【精神疾患で障害年金を申請する方へ】等級判定ガイドラインをわかりやすく解説でご覧ください。
統合失調症で障害年金はいくらもらえる?
令和7年度の年金額は以下のとおりです。
| 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
|---|---|---|
| 1級 | 1,039,625 円 ※子の加算額あり | 報酬比例の年金額×1.25 ※配偶者の加算あり |
| 2級 | 1,039,625 円 ※子の加算額あり | 報酬比例の年金額×1.25 ※配偶者の加算あり |
| 3級 | なし | 報酬比例の年金額 ※最低保証額623,800円 |
| 障害手当金 | なし | 報酬比例の年金額×2 ※支給は一度のみ |
高い給与を受け取り、厚生年金に長い期間加入していると、年金額は高くなる
障害年金は、障害からくる症状によりどのくらい生活や仕事に支障が出ているかにより等級が決定し、年金額が変わります。
「統合失調症だから」という理由で年金額が増減することはありません。
障害年金の金額をもっと詳しく知りたい人は障害年金でもらえる金額は?精神疾患だと年金額は変わる?社労士が解説!をご覧ください。
統合失調症での障害年金申請時に注意すべき3つのポイント
統合失調症で障害年金を申請するときに知っておきたい注意点は次の3つです。
- 診断書は「生活の困難さ」を正しく反映してもらう
- 診断書は必ずチェックする
- 整合性のある書類作りをする
それぞれ見ていきましょう。
診断書は「生活の困難さ」を正しく反映してもらう
障害年金の申請において、医師に作成してもらう診断書は、あなたの「生活の困難さ」を正確に反映していることが重要です。
医師は診察室での様子をもとに診断書を作成しますが、診察時間だけでは、あなたが統合失調症によって日常生活や仕事でどれほど困っているかをすべて把握することは難しいです。
そのため、診断書には、あなたの日常生活における具体的な困りごとや、家族・友人から受けているサポート、職場で配慮されていることなどを詳しく記載してもらうよう依頼しましょう。
診断書を依頼する際は、事前に以下のような内容をメモにまとめて医師に渡すことをおすすめします。
- 具体的にどんなことで困っているのか
(例:自炊ができない、入浴が週に1回程度、買い物に行けないなど) - 家族や友人からどのようなサポートを受けているのか
- 会社でどのような特別な配慮を受けているのか
(例:短時間勤務、残業なし、休憩室での休憩頻度など) - 利用している福祉サービスの内容や頻度
ふだんの診察から医師に自分の状況をこまめに伝えることが理想的ですが、難しい場合は、ご家族に診察に付き添ってもらい、あなたの状況を医師に伝えてもらうのも良い方法です。
診断書こそが、あなたが統合失調症で障害年金をもらうためのカギとなります。
無理なく医師と意思疎通ができるように、自分なりのやり方を探してみましょう。
診断書は必ずチェックする
医師から受け取った診断書は、必ず内容を確認しましょう。
たとえ封筒に入れられ封印されていても、ためらわずに開封してチェックしてください。

診断書を受け取ったら、まずご自身の統合失調症の症状や、日常生活で困っていることが正しく反映されているかを確認しましょう。
具体的には、「生活の困難さ」を示す情報(例:金銭管理の状況、身の回りのこと、対人関係など)が盛り込まれているか、また、障害年金の審査に必要な項目がすべて記載されているかを念入りに確認してください。
診断書のチェックを怠ると、申請しても「統合失調症なのに障害年金がもらえない」という結果になりかねないので、慎重に進めましょう。
整合性のある書類作りをする
障害年金の申請では、提出するすべての書類間で内容に矛盾がないよう、一貫性を持たせることが重要です。
障害年金の審査では、診断書だけでなく、あなたの病気の経過や日常生活の状況を記す病歴・就労状況等申立書など、提出するすべての書類の内容が一貫しているかどうかがチェックされます。
例えば、診断書には「軽度の統合失調症」と書かれているのに、ご自身で作成した申立書には「毎日何もできず、ほとんど寝たきりの状態」といった「重症」を思わせる内容が書かれていたら、審査官はどちらを信用してよいか判断に迷ってしまいます。
このような矛盾があると、結果的にあなたの障害の程度が正しく評価されず、「障害年金がもらえない」という結論に至る可能性が高まります。
ご自身やご家族だけで整合性のある書類を作成するのが難しいと感じる場合は、障害年金専門の社会保険労務士(社労士)に相談することをおすすめします。
適切な書類作りは、統合失調症で障害年金を受給するための大切なステップです。
障害年金の申請代行を社労士に依頼するメリットは?
障害年金の申請を社会保険労務士(社労士)に依頼すると、複雑な手続きや専門的な書類作成の負担が大幅に軽減され、受給の可能性が高まります。
最大のメリットは、書類不備や記載内容の不十分さを防げる点です。
障害年金の審査では、診断書や病歴・就労状況等申立書など、提出書類の記載内容が結果を大きく左右します。
社労士は、提出書類が障害認定基準に沿っているかを精査し、あなたの統合失調症による実際の困難さを正確に伝えられるように作成をサポートしてくれます。
また、医師とのコミュニケーションに不安がある場合でも、社労士は心強い味方になります。
診断書の依頼方法について具体的なアドバイスをしてくれたり、場合によっては医師との間に入って、あなたの症状や日常生活の状況が適切に診断書に反映されるよう橋渡しをしてくれたりします。
これにより、医師があなたの状態を正しく理解し、適切な診断書を作成してくれる可能性が高まります。
「統合失調症で障害年金はもらえない」と諦める前に、専門家の力を借りることも選択肢に入れてみましょう。
社労士へ申請代行については障害年金の申請を依頼するメリットは4つ!【社労士の選び方もわかりやすく解説】で詳しくご紹介しています。
まとめ
統合失調症は、障害年金の支給対象となる疾患です。
障害年金の3つの受給条件をすべて満たせば、統合失調症で障害年金が受給できます。
診断書や病歴・就労状況等申立書の記載内容に自身の困りごとや周囲のサポート内容が正しく記載し、審査官に伝わる書類作りをすることが大切です。
自分や家族で提出書類が作れなかったり、医師との意思疎通に不安を感じたりする場合は、障害年金専門の社労士へ相談してみましょう。
精神疾患専門のゆうき事務所では、経験豊富な社労士が丁寧にヒアリングを行い、あなたやご家族の障害年金申請をサポートします。
統合失調症を含む精神疾患での障害年金申請にお困りの際は、ゆうき事務所にお気軽にご相談ください。
まずは無料相談から始めませんか?
障害年金の専門家が、あなたの状況に合わせて
丁寧にサポートいたします
受付時間:平日 09:00〜18:00

