更新日:2025.08.30
双極性障害で障害年金はもらえる?申請の流れやポイントを社労士が解説
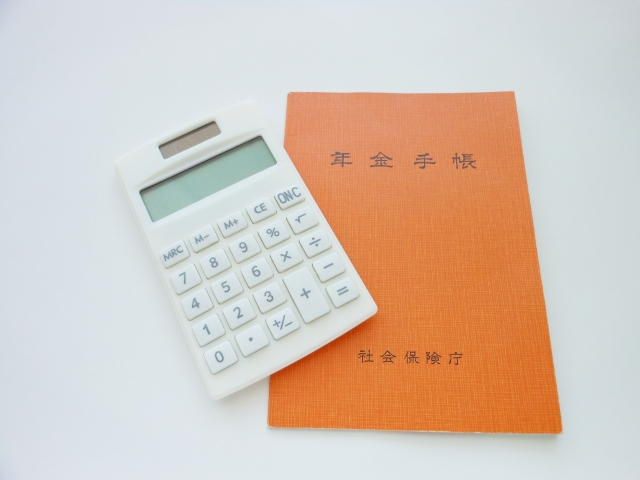
双極性障害の症状によって働けず、経済的な不安を抱えている方は少なくありません。
「障害年金はもらえるのだろうか?」と疑問を持ちながらも、制度の仕組みが複雑で一歩を踏み出せないという声も多く聞かれます。
双極性障害は「躁状態」と「うつ状態」の両方があり、症状の出方や生活への影響が人によって大きく異なるため、申請が難しくなりやすい特徴があります。
この記事では、双極性障害と障害年金について、次のような内容をわかりやすく解説します。
- 双極性障害でも障害年金の対象になるのか
- 障害年金の受給要件
- 申請の流れ(初診日の証明、診断書、病歴就労状況等申立書など)
- 申請で注意したいポイント
- 社労士に相談するメリット
障害年金は、生活を支える大切な制度です。正しい知識を持つことで、申請に向けて安心して第一歩を踏み出せます。
双極性障害で悩むあなたやご家族にとって、少しでも参考になる情報をまとめていますので、ぜひご覧ください。
目次
双極性障害で障害年金はもらえる?
結論からお伝えすると、双極性障害で障害年金を受け取ることはできます。
双極性障害は「気分障害」に分類され、うつ病などと同じように障害年金の対象です。
ただし、双極性障害だからといって自動的に障害年金が支給されるわけではありません。
双極性障害の認定基準は、症状により「日常生活にどれほど支障が出ているか」です。
例えば、「うつ状態のときに仕事や家事ができない」「躁状態だと衝動的な行動で生活が乱れてしまう」など、社会生活に困難がある場合には受給の可能性があります。
つまり、双極性障害と診断されていても、症状が軽くふだんの生活に大きな支障がない場合は障害年金は認められないということです。
日常生活や就労に支障が出ていれば、障害年金の対象として認定される可能性があります。
双極性障害はⅠ型とⅡ型ともに障害年金の対象
双極性障害はⅠ型・Ⅱ型のどちらも障害年金の対象です。
双極性障害には大きく分けてⅠ型とⅡ型があり、症状の現れ方は異なりますが、どちらも日常生活に支障が出る病気であるため、障害年金の支給対象となります。
Ⅰ型は、極端な躁状態が特徴で、寝ずに活動し続けたり、次々にアイデアが浮かび、話が止まらなくなったり、浪費や衝動的な行動をとったりするなど、周囲とのトラブルを起こすことがあります。
場合によっては、入院が必要になるほど症状が激しくなることもあります。
一方でⅡ型は、Ⅰ型ほど激しい躁状態は見られませんが、うつ状態が長く続く傾向が強く、自殺リスクも高いため注意が必要です。
双極性障害Ⅰ型もⅡ型も、症状の重さや生活への影響を踏まえて、障害年金の審査が行われます。
どちらの型でも、日常生活に支障がある場合には障害年金の申請を検討してみましょう。
双極性障害Ⅰ型とⅡ型の違い一覧
双極性障害Ⅰ型とⅡ型の違いを、下表にまとめました。
| 特徴 | 双極性障害Ⅰ型 | 双極性障害Ⅱ型 |
|---|---|---|
| 躁状態の程度 | 激しい | 比較的軽い |
| 社会生活への影響 | 大きな支障をきたす | 著しい支障はないことが多い |
| 本人の自覚 | 病識がないことが多い | 「調子が良い」と感じ、病気と自覚しにくい |
| うつ状態 | 期間はさまざま | Ⅰ型よりも長く、重い傾向がある |
Ⅰ型とⅡ型では現れる症状は違いますが、日常生活に支障があれば障害年金が受給できる可能性があります。
双極性障害で障害年金を受給するための3つの条件
双極性障害で障害年金をもらうには、次の3つの条件をすべて満たすことが必要です。
| 初診日要件 | 双極性障害の症状で初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること |
| 保険料納付要件 | 初診日の前日までに、一定期間の年金保険料を納付していること |
| 障害状態要件 | 初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)に、国が定める障害等級に該当すること |
双極性障害は症状に波があるため、障害状態要件の判断が難しいこともあります。
また、保険料の未納が多い場合は、納付要件を満たしているかどうかの確認が複雑です。
ご自身や家族だけで判断せず、障害年金に詳しい社労士に相談することをおすすめします。
障害年金の受給条件の詳細は、関連記事をご覧ください。
▶障害年金の3つの受給条件とは?年齢は関係ある?わかりやすく解説!
▶【精神疾患で障害年金を申請する方へ】等級判定ガイドラインをわかりやすく解説
双極性障害での障害年金申請の流れ
双極性障害で障害年金を申請する際は、段階を追って進めることでスムーズに手続きを行えます。
まず 「初診日」と「保険料納付状況」を確認し、「初診日を証明できる書類」を準備します。
その後、主治医に「診断書」を依頼し、日常生活や就労の状況をまとめた 「病歴・就労状況等申立書」を作成します。
さらに、請求書やその他必要書類をそろえて年金事務所に提出 します。
簡単に流れをまとめると次のとおりです。
- 初診日を確認
- 保険料納付状況を確認
- 初診日証明書類の準備
- 診断書の取得
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- 請求書・その他書類の準備
- 年金事務所に提出
障害年金の請求書を提出後、審査には通常2~3か月かかり、障害年金の支給開始はさらに1か月ほど要します。
障害年金申請の詳しい流れは、下記の関連記事をご覧ください。
▶【障害年金の手続きをスムーズに進めたいあなたへ】申請の流れをわかりやすく解説
双極性障害で障害年金をもらうのが難しい理由
双極性障害で障害年金をもらうのは、簡単ではありません。
ふだん書類作成をしていない人にとって、躁状態とうつ状態で起こる症状や日常生活での支障を書面でわかりやすく伝えることは難しいと感じることが多いです。
双極性障害は、気分が大きく高揚する「躁状態」と、気分が沈み込む「うつ状態」とを繰り返す病気です。
これらの症状は時期によって全く異なり、日常生活への影響も大きく変化します。
そのため、障害年金を申請する際には、両方の状態を的確に記録し、生活への支障を客観的に伝える必要があります。
申請で後悔しないための注意点
双極性障害で障害年金の申請をする際は、書類の内容や診断書の記載が適切であることが大切です。
症状に波がある病気なので、一時的に元気に見える時期だけが評価されると、生活上の困難が審査する人に正しく伝わらないことがあります。
そのため、以下のポイントを押さえて申請の準備をしましょう。
1. 診断書に症状の両面を反映してもらう
双極性障害で障害年金を申請する際には、診断書にうつ状態と躁状態の両方を正確に記載してもらうことが重要です。
通院時の様子がたまたま躁状態やうつ状態の一方に偏っていると、もう片方の症状や生活への支障が診断書に十分反映されないことがあります。
そのため、診察の際にはそれぞれの状態でどのような困難があるのか、日常生活や仕事への影響も具体的に伝えましょう。
診察時間が短く伝えきれない場合は、事前に症状や支障をまとめたメモを用意することをおすすめします。
躁状態とうつ状態それぞれの影響を整理して伝えることで、診断書の作成に必要な情報を医師と共有でき、障害年金の審査で正しく評価されやすくなります。
なお、障害年金審査のカギとなる「診断書」については、関連記事で詳細をお伝えしています。
▶障害年金の審査は診断書で決まる?知っておきたい注意点と社労士のサポート
2. 日常生活の実態を「病歴・就労状況等申立書」に正確に書く
障害年金の審査では、診断書だけでなく「病歴・就労状況等申立書」に日常生活の実態を正確に書くことがとても重要です。
診察室での短いやり取りだけでは、双極性障害が生活にどのような影響を与えているのかが十分に伝わらないケースが多くあります。
病歴・就労状況等申立書は、ご本人やご家族が日常生活で直面している困難をありのままに示す資料です。
日常生活の様子を余すことなく、かつ要点を絞って記載しましょう。
以下は、うつ状態のときと躁状態のときの記入例です。
【病歴・就労状況等申立書への記入例】
| うつ状態のとき | ・気分が落ち込み、1日中ベッドから起き上がれません。 ・家事は手をつけられず、買い物や外出もできません。 ・仕事も休んでしまい、生活が成り立たなくなります。 |
| 躁状態のとき | ・夜眠らずに動き続け、必要のない買い物で数万円を浪費してしまいます。 ・話が止まらず、職場や家庭で人間関係のトラブルが頻繁に起こります。 |
このように具体的なエピソードを交えて書くことで、障害年金の審査担当者に双極性障害の実態を正確に伝えることができます。
症状の波があるからこそ、ふだんの生活での困難を丁寧に記載することが大切です。
病歴・就労状況等申立書の詳細は、下記の関連記事でわかりやすくご紹介しています。
▶病歴・就労状況等申立書は障害年金の重要書類!書き方や記入例もご紹介
3. 「見た目の元気さ」に惑わされない
障害年金の申請では、双極性障害の「見た目の元気さ」に惑わされず、生活の困難さを正確に伝えることが大切です。
診察の場や周囲からは、躁状態のときに明るく元気に見えるため、「もう回復している」と誤解されることがあります。
しかし実際には、気分の高揚を抑えられず浪費や対人関係のトラブルが起きたり、自分の行動を制御できず苦しむことも少なくありません。
障害年金の審査で見られるのは外見の印象ではなく「生活にどの程度支障があるか」です。
そのため、うつ状態で動けない時期と躁状態でトラブルが生じる時期、両方の実態をバランスよく病歴・就労状況等申立書や診断書に記載することが大切です。
双極性障害による日常生活での困難を正しく理解してもらうことが、適正な審査へとつながります。
4. 書類作成は専門家に相談することもできる
障害年金の申請で迷ったときは、双極性障害に詳しい専門家へ相談することも選択肢のひとつです。
診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が不十分だと、受けられるはずの障害年金が不支給になったり、低い等級で決定されてしまうことがあります。
特に双極性障害は、躁状態とうつ状態の差が大きく、書類でその実態を的確に表すのは簡単ではありません。
そんなとき、障害年金に精通した社会保険労務士(社労士)に依頼すれば、書類作成のサポートを受けながら安心して申請を進めることができます。
無理に一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも、スムーズな障害年金申請への大切な一歩です。
社労士への依頼については、障害年金の申請を依頼するメリットは4つ!【社労士の選び方もわかりやすく解説】で詳しくご紹介しています。
双極性障害だと障害年金は何級になる?
双極性障害で障害年金を申請する場合、診断名だけで等級が決まるわけではなく、日常生活や仕事にどの程度支障があるかによって等級が決まります。
障害基礎年金では1級・2級、障害厚生年金では1級~3級までが対象です。
具体的な障害等級と状態は次のとおりです。
| 障害等級 | 障害の状態 |
|---|---|
| 1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
| 2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
| 3級 (障害厚生年金のみ) | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
参考:障害認定基準(57ページ)|日本年金機構
双極性障害では、躁状態とうつ状態の波が生活にどのような影響があるかを診断書や申立書に具体的に示すことが重要です。
この情報を正確に伝えることで、障害年金の等級判定がより適切に行われます。
障害等級ごとの年金額については、障害年金でもらえる金額は?精神疾患だと年金額は変わる?社労士が解説!をご覧ください。
双極性障害での障害年金申請でよくある質問
双極性障害での障害年金を申請する際に寄せられる質問に回答していきます。
双極性障害の初診日とはいつのことですか?
双極性障害で障害年金を申請する場合の「初診日」とは、双極性障害の症状で初めて医療機関を受診した日のことを指します。
診断名が「双極性障害」と明確に確定していなくても、症状がすでに現れていて、その症状について医師の診療を初めて受けた日が「初診日」です。
例えば、10年以上前にメンタルクリニックで「うつ病」と診断され、その後別の精神科で「双極性障害」と診断された場合でも、最初に症状で受診したメンタルクリニックの日が初診日として扱われます。
双極性障害は診断までに時間がかかるケースが多く、診療記録やカルテが残っているかの確認が重要です。
障害年金では、この初診日をもとに保険料納付要件や障害認定日が決まるため、正確な日付の確認と記録が受給の可否に直結します。
双極性障害で転院歴がある人は、これまでの通院歴を振り返って書面にまとめておきましょう。
障害年金の初診日については、関連記事でわかりやすくご紹介しています。
▶障害年金の初診日とは?カルテがないときの対処法もご紹介!
双極性障害で働いていますが、障害年金はもらえますか?
双極性障害で働いていても、障害年金の受給要件を満たしていれば受け取れます。
しかし、働いていると「障害の程度が軽い」と誤解されやすく、申請時には注意が必要です。
双極性障害の特徴である躁状態とうつ状態の波により、元気なときは通常通り働けても、うつ状態では出勤が困難で休みがちになることが多いです。
また、会社から特別な配慮を受けて、なんとか仕事が続けられるという人も見られます。
障害年金の審査では、このような日常生活や就労への影響が重視されるのです。
したがって、病歴・就労状況等申立書に、躁状態とうつ状態それぞれの働き方や休職の状況、仕事上の困難や周囲のサポートなどを正確に記載することが大切だといえるでしょう。
双極性障害の実態を正確に伝えることで、働きながらでも適切な障害年金の等級判定を受けやすくなります。
双極性障害での受給事例
ゆうき事務所にご依頼いただき、障害年金が受給できた事例をご紹介します。
双極性障害で働きながら障害厚生年金3級を受給できた事例
- 傷病名 双極性障害
- 30代女性
- 認定結果:障害厚生年金3級
- 支給額:年間約58万円 + 遡及分約150万円
【ご相談時の状況】
管理職に昇進したことをきっかけに、過労が重なり体調を崩され、双極性感情障害と診断されました。
現在は週4日ほど勤務できていますが、症状の波があり、いつ働けなくなるか分からない不安を抱えておられます。
将来の生活を考え、障害年金の申請を検討しご相談いただきました。
【相談から申請までのサポート】
障害認定日の時点から現在まで一般就労を続けていましたが、「働けていることで年金が受けられるのか不安」とお悩みでした。
詳しく伺うと、対人関係が難しいため特別に在宅勤務を認めてもらっていることや、病状を理解している経営者の配慮を受けながら就労を続けている状況が分かりました。
これらの事情を病歴就労状況等申立書に丁寧に記載しました。
さらに、仕事は何とかこなしていても、日常生活では同居のお母さまの全面的な介助が必要であることも合わせて記載しました。
【審査の結果】
今回のケースでは、障害厚生年金3級(年間約58万円)に加え、遡及分として約150万円の受給が認められました。
ご本人は30代とまだ若く、今後働けなくなるかもしれないという不安を抱えていらっしゃいましたが、今回の障害年金の受給決定により「生活に安心感が持てるようになりました」と喜びの声をいただいております。
まとめ
障害年金の申請は、制度や書類が複雑で「自分ひとりでできるのだろうか…」と不安を感じる方も少なくありません。
双極性障害の場合でも、日常生活や就労に支障がある方は障害年金を受け取れる可能性があります。
ただし、躁状態・うつ状態それぞれの影響を正しく記録し、診断書や申立書に反映させることが重要です。
「どう書けばよいのかわからない」と迷ったときは、専門家に相談するという選択肢もあります。
一人で抱え込まず、必要な情報やサポートを活用しながら、安心して申請を進めていきましょう。
ゆうき事務所では、双極性障害の申請に精通した社労士が丁寧にサポートします。
「自分も対象になるのか知りたい」「申請を一歩進めたい」と思った方は、どうぞお気軽にご相談ください。

